大分県立新生支援学校小学部3年
フェルトボールの数を見て、何個と何個で5になるか合成・分解の表し方で答える学習
-
使用したICT機器
-
[機器]
タブレット
[教師が使用したツール]
デジタルソフト [生徒が使用したツール]
デジタルソフト
-
学校・学年
-
特別支援学校
大分県立新生支援学校 3年
-
教科
-
算数
-
障がいの状況
-
・手元の操作や視覚情報が多いと、集中が続かなくなるこ
とがある。
・集中が続かなくなるため、学習に消極的になったり、離席したりすることがある。
-
子どもを取り巻く状況
-
〈保護者の願い〉
・正確に10までの数を数えられるようになってほしい。
・実際の生活の場面で活用できるようになってほしい。
-
子どもの困り(本人の困り)
-
【算数】
・5までの合成・分解では、5マスのケースに4個フェルトボールを入れて提示し、「4と何個で5になりますか」と問いかけると、「2」と答えたり「3と2で5」と答えたりする。
-
解決の方策・手立て
-
・合成・分解の仕組みを一つひとつkeynoteのスライド(アニメーション)で提示することで、視覚情報が絞られ、理解することができる。
・表し方が分かり、成功体験が増えると、自信を持って取り組むことができる。
-
実践の様子
-
・5までの合成・分解の表し方がわかるように、Keynoteで5マスのケースのイラストと『4と?で5』等の問題を提示した。
・アニメーション機能を使用しながら
①5マスのケースに入った4個の●を水色の枠で囲って提示
②何も入っていない1個のマスを赤色の枠で囲って提示
③赤色の枠で囲ったマスに●が入っていく
の順で示し、『4と1で5』になることに気づくことができるようにした。
・合成・分解の表し方が分かるようになると、スライドで提示した問題と教師の「4と何個で5になりますか」等の問題を聞いて、5マスのケースのうち、空のマスを指さして「1個」と答えたり、数えて「4と1で5」と答えたりすることができた。
・Keynoteを使って学習したことで、プリント課題でも『4と□で5』や『3と□で5』等の問題に、「4と1で5」や「3と2で5」と答えたり、空欄に『1』や『2』と答えを書いたりすることができるようになった。








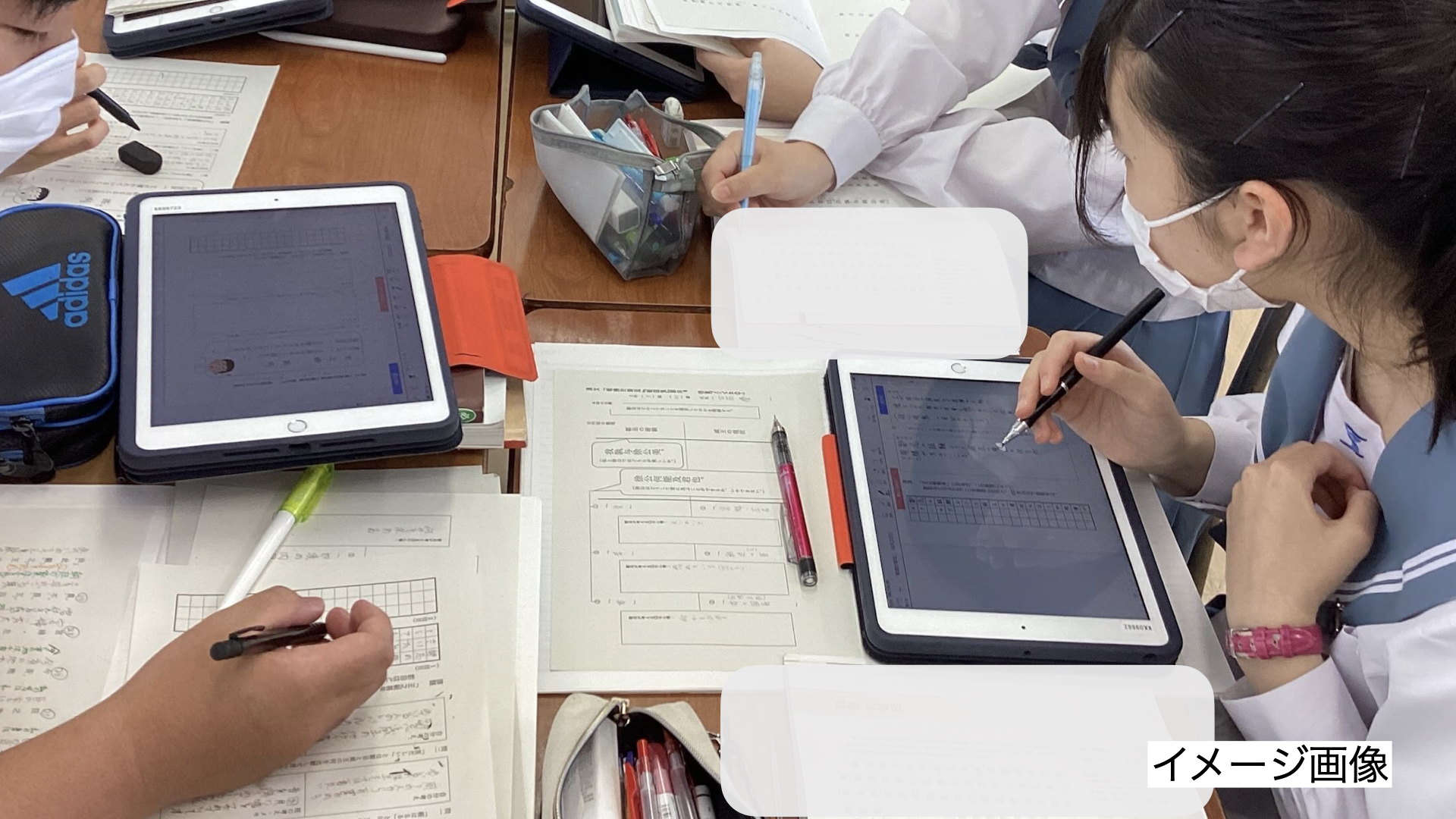

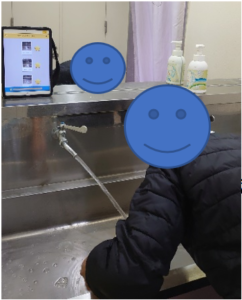
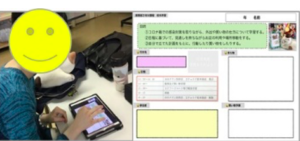
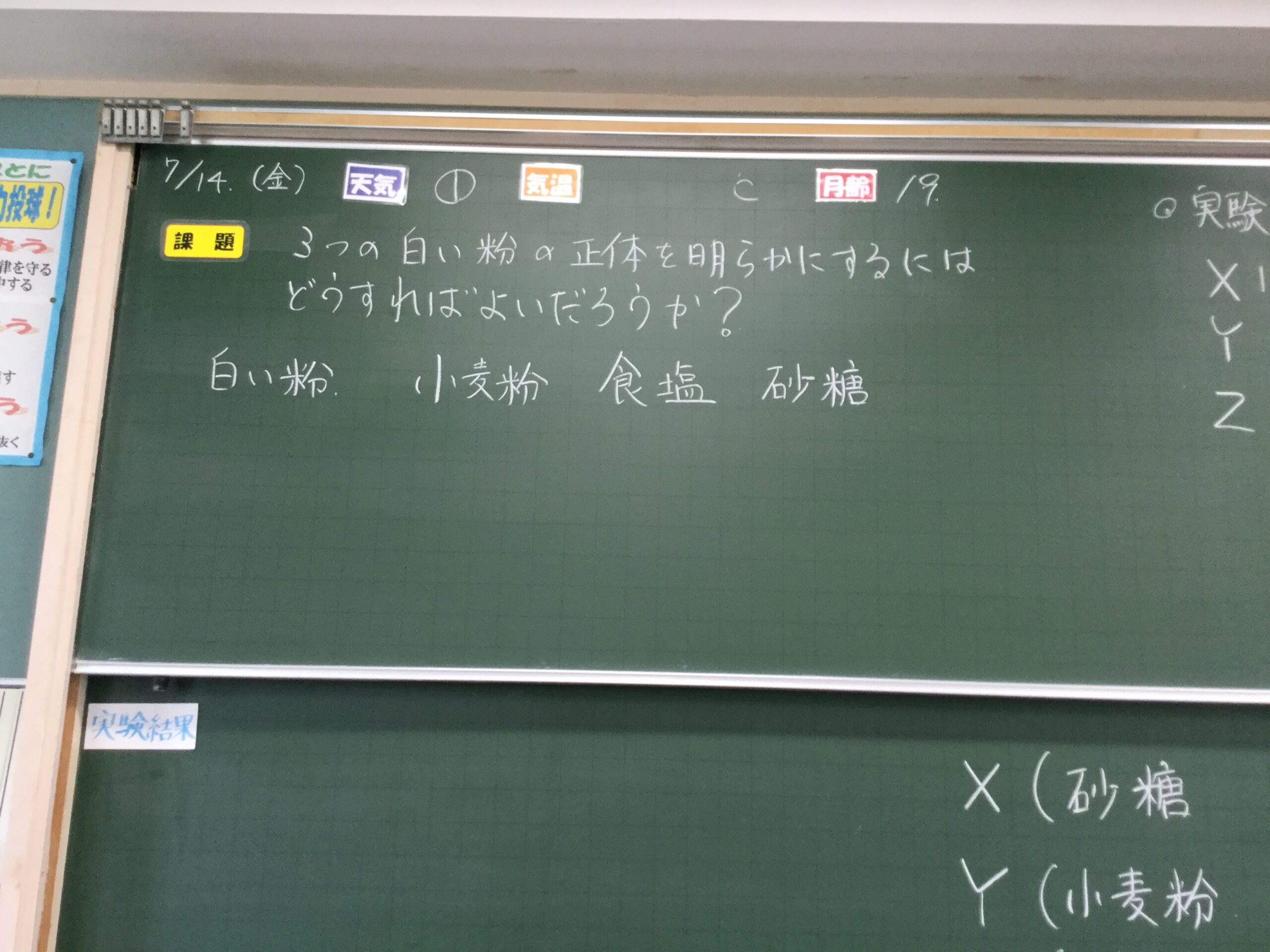
コメント